税金は所得に税率を乗じて計算されます。
所得は、『収入−経費』です。
所得が300万円を超える場合は、対策を講じれば、会社形態にした方が、節税となる可能性がでてきます。
さらに、所得が500万円を超える場合は、会社形態にして対策を講じることにより、50万円〜80万円の節税メリットを享受できます。
以下が会社形態で採用することができる具体的な節税対策です。
会社が役員に払う報酬は、会社側では、経費となり、会社の税金を減らします。
一方、社長個人側では、給与として所得税課税がされます。
「行ってこい」の印象を受けますが、給与が所得税課税されるときは、「給与所得控除」が差し引かれてから税率がかけられるので、「給与所得控除」の分だけ、税務上は有利です。
会社が社長に払う年間報酬が800万だとしましょう。
会社は、まず、800万円だけ課税所得を減らせます。
社長個人は、給与として800万円を所得税課税されます。
ただ、給与への課税は、給与所得控除200万円を差し引いてからの課税となります。
給与所得控除200万円×実効税率30%=60万円
の節税メリットを享受することができるのです。
②家族や親族を役員にする
家族の誰かに役員になってもらってその業務に対して報酬を払えば、その分を損金として計上できます。
役員報酬に対して所得税がかかりますが、他に収入がなければ、所得税をとても低く抑えられますので、結果としてかなりの節税になります。
家族二人に会社を手伝ってもらったとしましょう。
それぞれに年間100万円の役員報酬を支払い、かつ、その2人に他の収入がなければ、次の節税メリットを享受できます。
「年間役員報酬100万×2人×実効税率35%=70万円」
また、会社の場合には、5年以上勤続した役員に対する退職金は、税務上のメリットを受けることができます。
退職金の所得税の計算方法は、退職金額から退職所得控除を控除した金額をさらに2分の1にして分離課税をするので、税額は給与所得と比べて格段に少額となります。
さらに死亡時の退職金は、相続税の非課税枠がありますので、相続税法上も有利です。
④保険の活用
保険についは、個人事業の場合には、節税できる金額は僅少です。
しかし、法人の場合には、保険商品によっては、大きな節税メリットを享受できます。
解約したときに支払った保険料のほぼ100%と取り戻せるのに、支払時に保険料の50%〜100%を経費計上できる保険商品が節税商品としてよく活用されています。
⑤減価償却の計上
個人事業の場合には、減価償却は強制ですが、法人の場合には、任意償却です。
ですから、利益がでなかった年は、減価償却を実施せずに繰延べることができます。
⑥税率の差異
所得税と住民税を加えると、個人事業主の最高税率は、55%にもなります(2015年より。個人事業税は考慮せず)。
それに対して、法人の場合には、最高税率は、事業税を加えた実効税率でも、約35%です。
したがって、利益がたくさん出るのであれば、法人の方が、税率だけをみても有利です。
⑦欠損金の繰越控除
収入より、経費が大きいと(収入−経費)が赤字となります。
この赤字を欠損金といいます。
欠損金は、青色申告を要件に翌期以降に繰越し、課税所得金額から控除することができます。
翌期以降の税金を減らせる効果があるということです。
この繰り越せる期間が、個人事業は3年間であるのに対して、法人の場合は、9年間繰り越すことができます。
法人の場合には、より長く赤字を繰り越せるので、将来の課税所得と相殺して、より大きな節税メリットを享受できる可能性が高くなります。
⑧消費税の節税
- 期首の資本金が1,000万円以上。
- 2期前の課税売上高が1,000万円超
- 前期の最初の6ヶ月の課税売上および給与等支払額がともに1,000万円を超えたとき。事業規模が急速に大きくなったときは免税期間が短縮されるのです。
したがって、資本金1,000万円未満の会社を設立した場合は、事業規模が急速に大きくならない限り、すくなくとも設立2期目までは、消費税は課税されません。
課税売上高が1,000万円を超えた事業年度の2年後の事業年度にはじめて消費税がかかります。
ですから、個人事業者が、課税売上が1,000万円を超えてしまったら、その年から2年を経過する前に、資本金1,000円未満の会社を設立し、ビジネスを「法人成り」させれば、事業規模が急速に大きくならない限りは、さらに法人成り後の2年間も、消費税の課税義務を免れる免税メリットを享受できます。
⑨相続上のメリット
個人事業の場合、保有するビジネスで使っている資産等はすべて個別に相続の対象となります。
税金の納付を行うために、相続したビジネス用の資産を売却して現金化して納付したり、特例で認められる物納により税金を納めたりすることにより、重要な事業用資産が処分されてしまうといったことが少なくありません。
保有していた土地や建物、運転資金等が、分散して相続されることにより、事業用資産が分散することもあります。
また、個人事業の場合は、個人が許認可を取得しているので、事業者が死亡することにより、許認可の継続が困難となったりすることもあります。
こういった事態が発生すると、ビジネスの継続そのものが難しくなります。
そうなると、ビジネスに従事している家族や従業員の生活が脅かされることになります。
これに対して、「法人」の場合、株式の過半数を、ビジネスの承継者が相続すれば、経営を継続することは、比較的に容易です。
これは、事業承継対策上は、大きなメリットといえます。
経営者以外が持っている株式についても、定款に「株式の譲渡制限」を規定しておけば、第三者に譲渡されることを防止することができます。
- 均等割税額(最低7万円)は、赤字であっても発生します。
- 接待交際費は、年間800万円超えると損金にできません。年間800万円を超えると使った分だけ税金が比例的に減るという効果がなくなります。一方、個人事業の場合には、接待交際費は全額損金にできます。ただ、どちらの場合も社長個人の飲み食い等のために使った支出はそもそも接待交際費に該当せず、損金にはなりません。税務調査の際には、個人事業の方が、事業主個人の飲み食いのために支出されたのではないかというチェックがより厳しく行われる傾向があります。
▼会社設立の基礎知識
- 設立報酬0円コース 創業パック0円!さらに210,000円OFF
- 標準報酬コース 会社設立だけの標準サービスです
- お客様にやっていただくこととスケジュール 設立手続の具体的な流れです
- 会社設立サービスの内容 設立から、融資、補助金、社会保険までワンストップ対応します
- 会社経営成功の秘訣 成功した経営者の共通項をまとめました
- 資金計画をつくろう 資金ショートしないかを確かめましょう
- 株式会社の仕組み 『有限責任の原則』と『所有と経営の分離』を理解しよう
- 会社設立のメリットとデメリット 個人事業と徹底比較しました
- 会社設立の節税メリット 税金に関するメリットとデメリットを把握しよう
- 会社設立の失敗事例 他人の失敗から学ぼう
- 基本事項 会社を設立するときにあらかじめ決めておかなければならないこと
- 資本金について 資本金の決め方を解説します
- 現物出資 物を出資して資本金を増強しよう
- 株式会社と合同会社はどっちが得か? 合同会社は本当に得でしょうか?
- 会社設立手続の流れ 設立手続きの基本を理解しましょう
- 定款とは? 『会社の根本原則』の決め方を開設します
- 電子定款とは? 定款も電子化しています
- 払込証明書の作り方 資本金の証明の仕方です
- 会社印鑑の基礎知識 印鑑の基礎知識をまとめました
- 会社設立申請手続 登記申請書の具体例です
- 印鑑届出 会社の印鑑の届出方法です
- 登記事項証明書と印鑑証明書の取得の仕方 設立後の各種手続きに必要となります
- 銀行口座の開設方法 会社の銀行口座の開設方法を理解しましょう
- 税務署などの諸官庁への届け出 諸官庁への届出を怠ると損をします
- 主な許認可について 許認可なしに営業をすると厳しい処分を受けます
- 会社設立Q&A 会社設立、運営のための基本知識をまとめました
▼無料説明会のご案内
- 会社設立報酬0円コース
- 創業融資の無料相談会実施中! 最大2,000万円
- 補助金・助成金サポート! 最大200万円
工藤公認会計士
税理士事務所
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-14 第32荒井ビル3階
アクセス
JR市ヶ谷駅から靖国通りを靖国神社へ向かって4分です。
東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩4分
東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」徒歩4分
都営新宿線「市ヶ谷駅」A4出口徒歩2分
営業時間
9:00~18:00
著作紹介

【かんき出版】
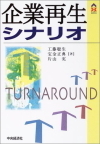
【中央経済社】
会社設立、創業融資、補助金・助成金について数冊の本を出版しております。




