持分会社の特徴を教えてください。
持分会社の特徴は次のとおりです。
① 社員全員で定款を作成し、その取り決めにより利益が分配されたり、会社運営がなされたりします。定款を変更するときも原則として社員全員の同意が必要となります。
② 業務は社員が行います。そのかわり、経営に失敗し借金が残った場合の責任も負うことがあります。会社債権者に対して無限に責任を負わなければならない無限責任社員だけでなく、出資の限度でしか責任を負わない有限責任社員も、会社債権者に対して直接責任を負うことになります(株式会社の株主の責任もその出資価額を限度としていますが、株主は会社債権者に対して直接に責任を持っているわけではありません。)。
③ 社員全員の同意がない限り、社員権の譲渡も新社員の加入もできません。
以上①から③の特徴から、持分会社は、社員間同士で信頼関係を保ちながら、自ら責任を取りつつも思いどおりに運営したいという、少人数で小規模の会社に向いているといえます。
株式会社と持分会社のどちらを選択すればよろしいでしょうか?
持分会社は、定款で自由にルールを決めて、それに基づいて会社を運営することができるため、会社設計の自由度が高く運用がしやすいように思われています。
しかし、そのルールの取り決めは容易ではなく、社員間で後日紛争が起きないようにするべく、きちんとした定款を作成しようとするならば、法律の専門家に依頼して定款を作成してもらうことになり、そのための報酬も用意しなければなりません。また、定款の作成に当たり、専門家と協議を進めるためには、株式会社との相違点や持分会社の設立や運用に関してある程度の知識を備えておかなければなりません。そのため、持分会社の扱いは初心者にとっては少し難しいと言えるかもしれません。
そして、持分会社には知名度とそれに付随するイメージの問題もあります。
株式会社はとても知名度が高いため、自分の会社が株式会社であるならば、自己紹介の度に株式会社がどういうものなのかを説明する必要はありません。株式会社ということでこれから発展していくイメージを抱いてもらうこともできるかもしれません。
一方で、持分会社の場合、株式会社ほどの知名度は無く、少人数・小規模の会社というイメージがあるため、発展していくという良いイメージをなかなか持ってもらえないかもしれません。仮に持分会社を設立して、クライアントと商談することになったとき、先方が持分会社についてあまり知識が無い場合、持分会社の業務執行方法や、債務の負担者が誰になるのかなどについて説明を求めてくるかもしれません。そうなってしまうと、せっかくの商談のために確保してもらった時間が、本筋から外れた説明で削られてしまうことになります。
以上の理由から、初心者の会社設立には株式会社が適しているのではないかと考えております。
取締役会を置くことのメリットとデメリットを教えてください
新会社を設立するに当たり、取締役会を設置するかどうかの選択のポイントは、ずばり役員の人数を無理なくそろえられるかどうかです。
取締役3人と監査役1人、合計4人の役員をそろえることができず、両親や祖父母などの親族を役員にしている会社も多く見受けられますが、役員には一定の法的責任もあるため、無理をして人数を集めることはおすすめできません。このような場合であれば、取締役会を設置しない会社を選択する方が良いでしょう。
そして、4人の役員を無理なくそろえることができるという場合には、次の『取締役会設置のメリット』と『取締役会設置のデメリット』を見比べたうえで、取締役会を設置するかどうかの判断をしてください。
(1)取締役会設置のメリット
① 株主総会の決議を要せず、取締役会で迅速に会社経営における具体的な意思決定を行うことができます。
② 取締役会を置くことで、対外的に組織のしっかりとした会社であるとみられることがあり、信用を高めることができます。
③ 特定の取締役が、自分だけの考えで勝手に物事を決めて取引をしたりすることなどを防止することが期待できます。
④ 取締役会の決議により、一事業年度の途中に1回だけ剰余金の配当(金銭配当に限定されます。)をすることができる旨を定款で定めることができます。
(2)取締役会設置のデメリット
① 取締役3人と監査役1人、最低4名の役員が必要であるばかりでなく、場合によってはその人数分の役員報酬を用意しなければなりません。
② 取締役役会を設置していない会社は株主総会の招集の手段に制限はなく、口頭でも株主総会の招集の通知は可能ですが、取締役会設置会社の場合、原則的に、株主総会の招集の通知を書面でしなければなりません。
③ 取締役会設置会社は、取締役会非設置会社と異なり、定時株主総会を招集するにあたって計算書類や監査報告書を添付しなければなりません。
株式会社を新しく設立するにあたって事前に決めておいた方が良いことは何でしょうか?
株式会社の新設の意思を固めましたら、手続きをスタートする前に、下記する会社の基本事項を決めてください。
この基本事項は、株式会社にとって憲法とも言える「定款」に盛り込まれることになります。
とても大切な事項ばかりですので、検討には慎重を期してください。
【会社の基本事項】
1.会社の商号
2.会社の本店所在地
3.会社の事業目的
4.会社の資本金の額
5.1株の払込金
6.会社の公告方法
7.取締役・監査役候補者の氏名
8.取締役・監査役の任期
9.事業年度
10.発起人の住所、氏名及び引受株式数
また、会社の設立に際して、事前にご用意頂きたい書類等は次のものが考えられます。
【事前にご用意頂きたい書類等】
1.印鑑証明書
発起人となられる方、そして代表取締役になられる方の印鑑証明書をご用意ください。
もし、設立する会社に取締役会を設置しない場合は、取締役になられる方全員分の印鑑証明書をご用意ください。
印鑑登録が無いと印鑑証明書を交付してもらえませんので、まだ登録を済まされていない方は、住所地の市役所等に行って早めに準備しておくのが良いかと思います。
ただし、印鑑証明書には有効期限があります。取得した日から3ヵ月以内でなければ、登記の申請をする際に使用することができませんので、ご注意下さい。
2.会社の印鑑
新会社の設立登記には会社の印鑑が必要です。
会社の印鑑が必要になるのは、会社を設立してからではありません。
登記の申請書に添付する書類には、会社の実印になる印鑑で押印しなければならないものもあります。
実印は、登記が完了したら法務局に登録することになります。
会社の口座を作るためにも会社の実印の印鑑証明書が必要です。
これらの作業をスムーズに進められるよう、設立準備の早い内から専門店に発注しておくことをおすすめします。
株式会社の名前を漢字や平仮名ではなく、アルファベッドやアラビア数字を使いたいと思っていますが、大丈夫でしょうか? また、会社の名前を決めるに当たり、気を付けなければならないルールのようなものがあれば、教えてください。
会社の名前のことを、商号といいます。この商号を登記するためには、細かいルールがありますので、注意してください。
まず、商号に使用することができる文字ですが、次の5種になります。
【商号に使用できる文字】
1.平仮名
2.片仮名
3.漢字
4.アルファベッド(AからZまでの大文字および小文字)
5.アラビア数字(0から9まで)
なお、ローマ数字(Ⅰやⅰなど)は使うことができません。
そして、商号には使用することができる符号があります。これらの符号を除く記号、図表、紋様などは商号として登記することができません。
【商号に使用できる符号】
1.「&」(アンパサンド)
2.「’」(アポストロフィー)
3.「,」(コンマ)
4.「‐」(ハイフン)
5.「.」(ピリオド)
6.「・」(中点)
なお、「 ( 」、「 ) 」(カッコ)は使うことができません。
符号は、原則的に、字句を区切る場合にのみ使用することができます。アルファベットだけでなく、平仮名、片仮名、漢字の字句についても同様です。ただし、「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして、末尾に使用することができます。
【符号の使い方】
| 符号の使い方 | 可否 |
| 株式会社Japan,コンサル | ○ |
| 株式会社Japanコンサル, | ×(字句を区切っていないから) |
| 株式会社Japanコンサル. | ○ |
| 株式会社.Japanコンサル | ×(字句の先頭にあるから) |
その他、商号を決定する上で注意を要する事項を列挙していきます。
【同一商号・同一本店の禁止】
すでに他の会社が、これから新設する会社の商号と同一の商号で登記しており、かつ本店所在地も同一である場合、その商号を登記することができません。同一の商号とは商号の表記が同じであることを意味しますから、例えば「株式会社JAPAN」と「株式会社japan」は、読み方こそ同じですが表記は異なるため、同一商号ではないと判断できます。
【「株式会社」を使用する】
株式会社は、商号の中に「株式会社」という文字を使用しなければなりません。付ける位置は商号の前や後のどちらでも構いませんが、「株式会社」の文字は漢字でなければならず、片仮名や平仮名にすることはできません。
【法令による制限】
「銀行」、「保険」、「信用金庫」、「信託」、「労働金庫」、「農業協同組合」、「商工会議所」などの文字は、当該事業を営む場合を除いて使用することができません。「バンク」についても同様に制限されますが、「データバンク」など、銀行と誤認されるおそれがない場合には使用することができます。
以上のような細かなルールに気を付けて、新会社の商号を決定してください。
ただ、以上のルールを踏まえて決定した商号でも、紛らわしい商号はトラブルの元ですので、おすすめはできません。
例えば、「トヨタ」、「バンダイ」、「ニッサン」などのように有名な商号を真似してブランドのイメージに便乗することは、他の会社が努力して築き上げた信用を無断で利用して利益を得るようなアンフェアな行為とされており、不正競争防止法で禁止されていますから、十分にご注意下さい。
法律が変わり、役員の登記の添付書面が変わると耳にしました。会社設立時に用意する書面にも影響があるのでしょうか?
平成27年2月3日に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。施行日は、平成27年2月27日とされており、この省令の施行により役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の登記を申請する際の添付書面が変更されることになりました。
改正の対象となる登記申請は、①株式会社の設立の登記の申請、②取締役・監査役の就任(再任は除きます。)による変更登記の申請とされていますので、会社設立時に用意する書面にも影響は及びます。
設立の登記の申請書には、取締役・監査役の就任承諾書に記載された氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(以下、「本人確認証明書」といいます。)を添付しなければなりません。ただし、登記の申請書に当該取締役の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付する場合は除かれるとされていますので、取締役会設置会社においては代表取締役に就任される方、取締役会を設置しない会社においては取締役に就任される方の場合、もともと添付書面として市区町村長が作成した印鑑証明書の用意を必要とされていましたので、別途本人確認証明書を用意する必要はありません。
【本人確認証明書の例】
1.住民票記載事項証明書(住民票の写し)
2.戸籍の附票
3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
4.運転免許証等のコピー
なお、「3.」と「4.」については、裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」旨の一文を記載し、記名押印する必要があります。
平成27年2月27日以降に会社設立をお考えの方は、本人確認証明書のご用意につき、くれぐれもご注意ください。
株式会社の目的を考えているのですが、どのようなところがポイントになりますでしょうか?
目的とは、その会社が行う事業の内容のことです。登記簿で公開される情報ですので、どんなことをする会社なのか、具体的にイメージできるような記載を心掛けてみてください。ポイントとしては次のようなものが挙げられます。
【同じ業種の会社を参考にする】
目的についても商号と同様に記載に関するルールが存在します。上場会社については、東京証券取引所などのホームページで定款が公開されていますから、同じ業種の会社の目的欄を参考資料として見ることができます。
【明確に表現する】
会社の目的は、一般の人が見てどのような事業かが分かるものでなければいけません。不明瞭な語句は用いることができませんし、特定の業界において定着している用語であっても、広く社会で認知されていなければ明確性を欠くことになりますので注意してください。明確性の判断基準としては、国語辞典や現代用語辞典に記載されているかどうかを参考にしてください。インターネットに掲載されているからといって、明確であるという考えは早計です。
【株式会社が行えない事業があります】
法令上制限を受けている事業については、会社で行うことはできません。例えば、弁護士、税理士、司法書士などの業務がこれに当たります。
【将来行う予定の事業もカバーする】
会社設立時に行う事業内容だけでなく、将来行う予定の事業を含めておいた方がいいと思います。目的に掲げた事業は、それを全て行わなければならないというわけではありません。もちろん、設立後に追加変更することもできるのですが、登記を変更しなければならなくなり、そのための費用がかかってしまいます。
▼会社設立の基礎知識
- 設立報酬0円コース 創業パック0円!さらに210,000円OFF
- 標準報酬コース 会社設立だけの標準サービスです
- お客様にやっていただくこととスケジュール 設立手続の具体的な流れです
- 会社設立サービスの内容 設立から、融資、補助金、社会保険までワンストップ対応します
- 会社経営成功の秘訣 成功した経営者の共通項をまとめました
- 資金計画をつくろう 資金ショートしないかを確かめましょう
- 株式会社の仕組み 『有限責任の原則』と『所有と経営の分離』を理解しよう
- 会社設立のメリットとデメリット 個人事業と徹底比較しました
- 会社設立の節税メリット 税金に関するメリットとデメリットを把握しよう
- 会社設立の失敗事例 他人の失敗から学ぼう
- 基本事項 会社を設立するときにあらかじめ決めておかなければならないこと
- 資本金について 資本金の決め方を解説します
- 現物出資 物を出資して資本金を増強しよう
- 株式会社と合同会社はどっちが得か? 合同会社は本当に得でしょうか?
- 会社設立手続の流れ 設立手続きの基本を理解しましょう
- 定款とは? 『会社の根本原則』の決め方を開設します
- 電子定款とは? 定款も電子化しています
- 払込証明書の作り方 資本金の証明の仕方です
- 会社印鑑の基礎知識 印鑑の基礎知識をまとめました
- 会社設立申請手続 登記申請書の具体例です
- 印鑑届出 会社の印鑑の届出方法です
- 登記事項証明書と印鑑証明書の取得の仕方 設立後の各種手続きに必要となります
- 銀行口座の開設方法 会社の銀行口座の開設方法を理解しましょう
- 税務署などの諸官庁への届け出 諸官庁への届出を怠ると損をします
- 主な許認可について 許認可なしに営業をすると厳しい処分を受けます
- 会社設立Q&A 会社設立、運営のための基本知識をまとめました
▼無料説明会のご案内
⇒創業融資の無料相談会実施中! 最大2,000万円
⇒補助金・助成金サポート! 最大200万円
工藤公認会計士
税理士事務所
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-14 第32荒井ビル3階
アクセス
JR市ヶ谷駅から靖国通りを靖国神社へ向かって4分です。
東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩4分
東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」徒歩4分
都営新宿線「市ヶ谷駅」A4出口徒歩2分
営業時間
9:00~18:00
著作紹介

【かんき出版】
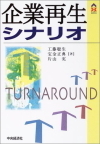
【中央経済社】
会社設立、創業融資、補助金・助成金について数冊の本を出版しております。




